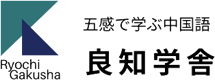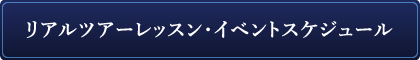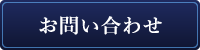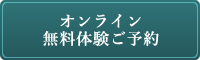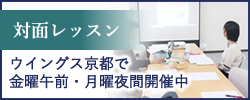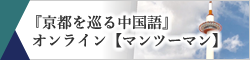- ホーム
- ブログ
ブログ
有栖川の野鳥
2022/10/11有栖川の野鳥
京都右京区を流れる有栖川は、嵯峨大覚寺のほとりから下嵯峨を経て、西高瀬川と交差し、桂川に注いでいます。
平成11年11月から地元、学校及び行政が有栖川の河川環境の向上や多自然川づくり等に取り組んでいて、
おかげで以前より随分環境がよくなり、常時、鯉や野鳥もいます。

さぎ【鷺】、中国語で”鹭lù,鹭鸶lùsī”

「さぎ」が付く慣用句で、「さぎを烏と言いくるめる」というのがありますが、
これは中国語で、”指鹿为马zhǐlù-wéimǎ《成語》;颠倒黑白diāndǎo-hēibái《成語》”といいます。
さぎといえば、こちらもさぎ【詐欺】
さぎ【詐欺】”欺诈qīzhà,欺骗qīpiàn,诈骗zhàpiàn”
例文:
さぎにあう|受骗
詐欺で金をだまし取る|诈骗金钱

単語を覚える時、全く別のものでも、このように関連付けて覚えるのも一つの方法です。
良知学舎では、テキスト一辺倒ではなく、生きた言葉を実際に使えるように工夫して授業を行っています。
一度、オンラインの無料体験会にご参加ください。
一度、見学にお越しください。
「弾道ミサイル」中国語の数え方
2022/10/10「弾道ミサイル」の数え方
先日の授業では「弾道ミサイル」を取り上げました。
「弾道ミサイル」は中国語で、”弹道导弹 dàndào dǎodàn”

例文:
北朝鲜10月6日早晨发射两枚弹道导弹。
Běicháoxiǎn 10 yuè 6 rì zǎochén fāshè liǎng méi dàndào dǎodàn.
ミサイルを数える量詞は枚méi、
この枚méi 、多くは形が小さい丸いものや、小型の平たいものや、丸い型の武器を数えます。
受講者の方から
「ミサイルを『枚』と数えるのは意外でした」との声を聞きました。
そうですね、日本語だと「発」ですが、「枚」だとなんか薄くて威力が弱そうな感じがしないでもない・・・。
「何はともあれ、まかり間違えば大惨事になるような
許しがたいこんな暴挙は決して許されるものではない」
岂有此理[qǐ yǒu cǐ lǐ] !
(そんな道理があるものか.そんなばかな話はない.もってのほかだ)
と受講者の方々、熱く語っていました。
良知学舎では対面レッスンも行っています。
場所は京都の中心部にあるウイングス京都。
朝のクラスですとレッスン終了後、クラスの方と一緒にランチや
四条通や百貨店でちょっとお買い物にも便利です。
対面レッスンについての詳細はこちらをご覧ください。
一度、見学にいらしてください。
地域発見!『堀川インご近所ガイドツアー』開催!!
2022/10/09地域発見!『堀川インご近所ガイドツアー』開催!!
良知学舎では京都堀川インとのコラボ企画として
地域発見!『堀川インご近所ガイドツアー』を開催中!
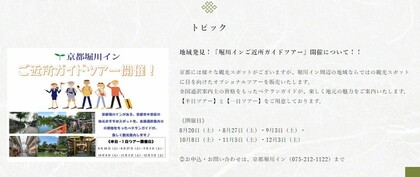
(京都堀川インのホームページより)
京都には様々な観光スポットがあります。
京都堀川イン周辺の地域ならではの観光スポットに目を向けた
全国通訳案内士の資格をもったベテランガイドが、楽しく地元の魅力をご案内するオプショナルツアーです。
このウォーキングツアーは日本語です。
《開催日》
8月20日(土)・8月27日(土)・9月3日(土)・
10月8日(土)・11月5日(土)・12月3日(土)
◎お申込・お問い合わせは、京都堀川イン(075-212-1122)まで
そして、インバウンド本格解禁に向けて
中国語と英語でも実施することになりました。

詳細は追ってお知らせいたします。
ようやく動き出す観光!
二条城、なにげに見える重要文化財
2022/10/08二条城、なにげにある重要文化財
今日は、二条城周辺で撮影でした。
撮影用に久しぶりに着物を着ました。

写真のバックにあるのが、二条城の「東南隅やぐら」です。
通りからなにげによく見えるこれ、なんと国の重要文化財。
城内の二の丸御殿は国宝。
二条城は1994年(平成6年)に、ユネスコ世界遺産に登録されました。
良知学舎ではこの見どころ満載の二条城を訪れて中国語を学ぶ
「京都を巡る中国語ツアーレッスン 二条城編」を実施中
今回は「上、下、出、回」などの方向補語を、体を使って実際の動作によって習得します。
講師の一方的な説明にならずに参加者の皆さんにも出来るだけ発音してもらう形式で、楽しく学んで頂きます。
受講料は\3,000(受講料には、当日配布の資料やプリントが含まれますが、二条城の入城料と二の丸御殿観覧料の1,300円は、各自別途現地でお支払い下さい。)
日程:
10月13日(木)
10月23日(日)
11月6日(日)
いずれも10時30分~12時
秋の二条城で楽しく中国語を学びましょう。
手書き力の衰え
2022/10/07手書き力の衰え
パソコンやスマホなどデジタル機器の普及で、9割の人が「漢字を手で正確に書く力が衰える」と考えていることが文化庁の世論調査で公表されました。
確かにパソコンやスマホではひらがなを入力すれば、自動的に漢字に変換してくれます。
正しい漢字を選択することはできても、いざその字を書く描くとなるとどう書くのだったか思い出せないと言う事はしょっちゅうあります。
手書きの文字には、書き手の個性も現れますよね。
丁寧な手書きの手紙はやはりいいものです。
(たまに達筆すぎて何が書いてあるかわからないことも、雑で汚いミミズが這ったような字でわからないこともありますが……。)
また繰り返し字を書くことで、脳が活性化され習得につながるそうです。
やはり手で書くことは大事なのですね。

てがき【手書き】 は中国語で、”手写shǒuxiě,手抄shǒuchāo”
例文:
手写的原稿
shǒuxiě de yuángǎo
手書きの原稿
习惯用电脑以后,手写的机会少了很多。
Xíguàn yòng diànnǎo yǐhòu,shǒuxiě de jīhuì shǎo le hěn duō.
パソコンに慣れてからは,手書きすることがめっきり減った。
手写输入
shǒuxiě shūrù
手書き入力
むかしは単語や文章を覚える時に書いて書いて書きまくっていました。
当時出来ていたペンだこも、今はもうへこんでいます。
-
 中国語の文法地獄を抜け出す方法
中国語の文法地獄を抜け出す方法みなさん、こんにちは。 大家好! 文法が壁になる理由中国語学習において、多くの方
中国語の文法地獄を抜け出す方法
中国語の文法地獄を抜け出す方法みなさん、こんにちは。 大家好! 文法が壁になる理由中国語学習において、多くの方
-
 中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統
中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統みなさん、こんにちは。 大家好!中秋节快乐!今日10月6日は十五
中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統
中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統みなさん、こんにちは。 大家好!中秋节快乐!今日10月6日は十五
-
 速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法
速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法みなさん、こんにちは。 大家好!先日、中秋節に関する中国語の音声を用意
速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法
速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法みなさん、こんにちは。 大家好!先日、中秋節に関する中国語の音声を用意
-
 中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現
中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を勉強していて
中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現
中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を勉強していて
-
 中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?
中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?みなさん、こんにちは。 大家好!先日、テキストに「风
中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?
中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?みなさん、こんにちは。 大家好!先日、テキストに「风