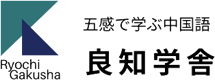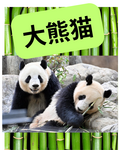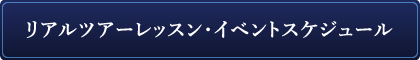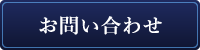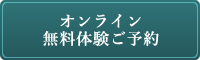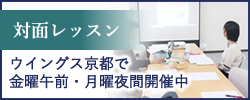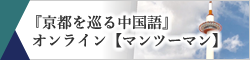- ホーム
- ブログ
ブログ
先生のマネはできるのに、自分で読むとグダグダ!? 中国語発音あるあると、その克服法
2025/07/21【 先生のマネはできるのに、自分で読むとグダグダ!?】中国語発音あるあると、その克服法
みなさん、こんにちは。 大家好!
「先生の言った通りに言えば通じるのに、自分で文章読むとあれ?声調どこいった?」
——そんな経験、ありませんか?
今回は、学習者さんの中でも特に多い“発音ギャップ”について、しっかり対策までご紹介します。
なぜ「マネはできるのに自分で読むと崩れる」のか?
この現象、実は脳内で行っている作業が全く違います。
「先生の音をマネする」は “耳→口”の模倣モード
「自分で文字を読む」は “文字→脳→音”の変換モード
後者は負荷が高くて、声調やリズムが崩れがちです。
だからこそ、ここを強化すれば自立した発音力がついてきます。
おすすめ練習法
シャドーイング:0.5秒遅れでモノマネする練習法
- やり方の詳細
音声再生と同時にスクリプトは見ないことからスタート → 最初は耳のみに集中。聞こえた音を、0.5秒ほど遅れて口に出します。 → スクリプトを見ながら練習するときもありますが、最初は“耳→口”の流れを強化するのが目的。
最初は一文のみをくり返す → いきなり段落は難しいので、短めの会話文を選びます。
慣れてきたらまとまった音声で練習 → 会話形式やナレーションの音声(1〜2分)を、意味理解よりも「音そのもの」を重視して何度も再現。
- 教材の選び方
テキスト+音声がセットになったものがおすすめ
発音が明瞭な素材から始めると、聞き取りやすく練習しやすい
- 声調を“歌のメロディー”のように意識する理由
声調は、中国語の「意味」を決める音の高低・変化。
日本語にはない概念なので、覚えづらいと感じる方も多いです。
そこでおすすめなのが「歌うようにまねる」こと。
- メロディー意識のポイント
第1声は高く平坦に「ピーン」と長く
第2声は「えっ?」と尋ねるように上げる
第3声は「あ~あ」と低く沈んで上がるカーブ
第4声は「うん!そう!」のように鋭く落とす
歌やCMのメロディーを覚えるように、声調にも「リズムと高さ」があると思って聞き取ると、意外と頭に残ります。
- 注意点
発音しようとするあまり、ピンインや意味を意識しすぎない
音に乗って口を動かすことに集中する
覚えようとするより「まねする」ことを優先する
こんな方におすすめです
発音はできるはずなのに、自分で読むと「あれ?」ってなる方
ピンインの世界に迷い込みつつある方
声調に人生を振り回されたくない方(笑)
もっと詳しく知りたい方へ
「ピンイン付きの例文で声調を意識しながら練習したい」 「録音してチェックしたいけど、どこを直せばいいか分からない…」 「先生のマネはできるのに、自分で読むと声調が迷子になる…それってなんで?」
そんな疑問や、学習のお悩みがある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ご質問やリクエストに合わせて、練習方法や資料についてもご案内しています。
「自分で読んでも通じる」発音を目指して、ご自身のペースで、楽しく取り組んでいただけるようサポートします。
「発音がうまくできない」と感じる瞬間は、自分の成長の入口でもあります。
うまくいかない理由が分かれば、対処法も必ず見つかります。
練習は地味で長い道のりかもしれません。
でも、自分の口から正しい音が出た瞬間の感動は、きっとあなたを次のステップへ連れていってくれます。
“聞けるだけ”から“読めても通じる”発音力へ。
発音で悩んだ分だけ、あなたの中国語はきっと深く、強く、面白くなっていきますよ。

-
 中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
-
 中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
-
 【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って