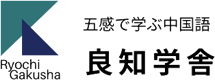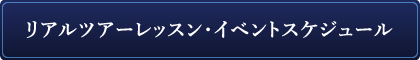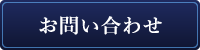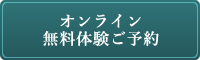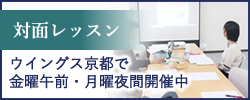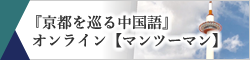- ホーム
- ブログ
ブログ
中国語、信任と信赖の違い
2023/02/18信任と信赖の違い
先日の授業で、”受到朋友的信任”(友達から信頼されている)という文章がありました。
そこで受講者の方から「信任」というのですね、信任と信頼はどう違うのですか、という質問がありました。
では一つずつ見て行きましょう。
信任
まず、信任 xìnrèn
(1)信用して任せる.信任する.
例文:
厂长很信任他/工場長はとても彼を信頼している.
那个人值得信任/あの人は信用できる.
对这种两面三刀l的人可信任不得/このような二枚舌の人間は決して信用してはいけない.
(2)信任.信頼.
获得信任/信頼を勝ち取る.
辜负信任/みんなの信任を裏切る.
信赖
そして信赖 xìnlài は
信頼する.信用し頼りにする、
信赖には”依靠”(頼る)ということが含まれているので、
「信赖」の方が「信任」より語意が重い感じです。
また”信赖”の対象は
人や組織のほか抽象的な事物も入ります。
例文:
可以信赖的人/信頼できる人
这项调查结果值得信赖/この調査結果は信頼に値する

まとめ
どういう時にどちらを使うかは難しいところですが、例文をたくさん見てまず感覚をつかんで、使ってみてください。同じ漢字で意味が違う中国語
2023/02/17同じ漢字で意味が違う中国語
同じ漢字で意味が違う中国語ってたくさんあります。
今回ご紹介するのは「大意」
日本語で「大意」って「概要、大体の意味」だと思いますが、
中国語では、「不注意である、うかつである」などの意味もあります。

日本語の「大意」の意味
① 大体の意味。あらましの意味。大義。
② 大きな志。大志。
(日本国語大辞典参照)
中国語の「大意」の意味
名詞としては、大体の意味,大意,粗筋
用例:
这篇论文的大意是这样的。/この論文の大意はこうだ。
略述大意。/大略を簡単に述べる。
把这篇文章的大意归纳一下。/この文章の大意を要約する。
そして形容詞としての用法では「不注意である,うかつである,いい加減である,油断している」という意味があるのです。
用例:
你千万不可大意。/君は絶対にいい加減にしてはならない.
大意不得/いい加減にしてはならない.
不要大意哦。/油断しないでね。
千万不要麻痺大意。/決して油断するな。
粗心大意/注意深くない。
粗心大意也要有个限度。/不注意にもほどがある。
あっちゃ~~!焦げちゃいました!たまにこんなこともあります。↓↓

うっかりしてはいけませんよ!
你可不能粗心大意哟!
と言われました。
中国の詩「二月の春風」
2023/02/16中国の詩「二月の春風」
二月中旬、まだまだ寒いです。
今回は二月にまつわる中国の唐時代の詩をご紹介します。
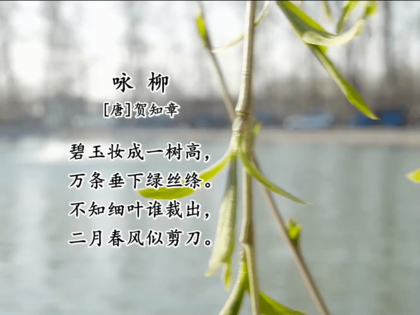
『咏柳 』
唐 · 贺知章
碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。
不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。
Bì yù zhuāng chéng yì shù gāo,wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo.
Bù zhī xì yè shéi cái chū,èr yuè chūn fēng sì jiǎndāo.
訳文
『柳を詠む』
唐 · 賀知章
翡翠色の若葉が柳の木を丸ごと飾りつけた、
細枝が何万本の緑リボンのように垂れ下がる。
新緑の若葉を切り出したのはだれだろうか。
それはハサミに似ている二月の春風だろう。
単語の解説
碧玉:翡翠色の玉。ここでは春の若葉を比喩します。
妆:飾る、装飾する。
一树:木の全体。一:全部、全体。ここの数詞は一定の数量を示すのではないでの要注意。次の「万」も同じように、具体的な数量ではなくて、おびただしい量という意味の誇張表現。
绦(tāo):シルクでできた紐状の織物。ここは柳の枝をたとえています。
裁:裁つ、切りそろえる、裁断する。
似:…のように。似ている。
概説
「柳を詠む」は、唐代の詩人、賀知章が書いた七言絶句です。
これは、物や事を題材にして詠まれた詠物詩です。
二月の新柳の柔らかで細やかな若葉が春風に吹かれている様子を表現し、早春の生命力の強さとその到来を喜ぶ詩人の気持ちを余すところなく詠いあげています。
二月の春風を「ハサミ」にたとえ、「切り出す」という擬人化された動作で表すという独自の発想で、目に見えない春風を実感のある生き生きとしたイメージに変えています。
独創的なだけでなく、第一句と第二句と第四句で、aoという韻を踏んでいます。
「二月の春風」ですが、この二月は旧暦の二月のことで、実際には二月の下旬から四月上旬ごろに当たります。
まとめ
古詩は難しいというイメージがありますが、わかりやすいのもたくさんあります。
上記のように詩の中の二月は旧暦の二月で今よりもまだもう少し先のことですが、今日まだこの寒い中に柳の若い葉が風に吹かれてたなびいているという情景を、季節を先取りして想像しながら、春の訪れを待つのも風流ですね。
でもまあ、二月の春風を「ハサミ」にたとえるとは、すごい発想です。
そうすると二月の春風は柳の葉を切るだけでなく、「切り絵」や「散髪」の達人だったりして!?
中国の学校、二学期始まる
2023/02/15中国の学校、二学期始まる
中国の学校は,小学(6年),初級中学(3年,中学校にあたる),高級中学(3年,高校にあたる)に分かれており,小学と初級中学の9年間が義務教育です。
中国の学校は9月入学の二学期制で,1~2月(春節期間)に約4週間の冬休み,7~8月に約7週間の夏休みがあり、今は冬休みが終わって二学期が始まる季節です。
中国でもコロナ禍でオンラインで授業が行われていました。
この二学期が始まる季節に中国のコラムに記事があったのでそれを日本語に訳しました。一部は原文を紹介します。
一番しんどかったのは親
長時間のオンライン学習で一番苦労したのは子どもたちなのでしょうか。
いえいえ、一番お疲れ様なのは生徒でも先生でもなく、全国の親御さんなんですよ!?
長期にわたるオンライン授業で、ずっと抑圧されてきた親御さんたちは、ようやく明るい展望が開けるようになったと感じています。
これまで、子どもの授業に熱心に取り組むあまり、子どもの言動のひとつひとつに、まるで手におえない小さな皇帝さまに仕えているような気持ちになっていましたが、 ようやく学校が始まろうとしている今、神獣がようやく檻の中に戻る希望が出てきたのです。
长时间的网课学习,最辛苦的是学生吗?不不不,最辛苦的不是学生,也不是老师,最最最辛苦的是全国各地的各位家长们!
随着很长一段时间的网课,让压抑很久的全国各地家长们总算有了盼头,曾经一心一意陪着孩子上课,孩子的一言一行,都让自己感觉像是伺候着一个惹不起的小祖宗,现在总算快开学了,神兽终于归笼迎来了希望。

全国の学校の2023年度スケジュールが出て、一番喜んだのは保護者たちでした。
子供を見ると憂鬱な気分になっていたのに、今やその子供がとても可愛く見えさえします。
子供たちが再び学校に通わなくなったら、おかしくなるのは私たちだと言う親がいても不思議ではありません。
会社では上司に、家では子供の勉強に悩まされ、まさに「死ぬより辛い」と言う親御さんもいるくらいです。
全国各地で進められている教育政策に基づき、各学校の二学期が始まったことに、全国の親御さんたちは大喜びしているのです。
いつからはじまる?
一般的には、小中学校の方が大学より早く始まり、大学は小中学校が始まってから半月、あるいはそれ以上遅く始まります。
浙江省、甘粛省、江蘇省の小中学校は2023年2月6日に二学期がスタートし、河北省の小中学校は2023年2月13日にスタートしました。
2023年の大学の開始は、例年より少し遅めになるようです。
天津医科大学は2023年2月16日、北京大学は3月8日、清華大学は2月28日の予定です。
学校に早くいきたい!?
このスケジュールが発表され、親が喜ぶだけでなく、家にいる大学生や専門学校生もついに家を出て美しい新世界へと駆け出すことができると安堵しています。
一方、新学期が始まるカウントダウンとともに、「家での快適さに慣れてしまって、学校での苦労に耐えられない」という子供ももいます。
そんな子供が久しぶりの学校生活をスタートするにあたってのヒントとして、
クラスメートとオンラインで積極的にコミュニケーションをとり、事前に打ち解けることも大切です。
新学期を迎え、クラスメイトと会って、えっと~君の名前は......君の名前は......何だった?とならないように。
最後に
新学期、新しい希望、学校の足音が聞こえてくる中、みんなそれぞれ自分のビジョンや目標を持っていると思います。
人生で最高の思い出は、学校生活です。
今、慣れてしまった、あるいは飽きてしまったと感じる学校生活も、近い将来、最高の思い出になり、今、ストレスを感じている勉強や苦労も、後々、最高の思い出のひとつになるにちがいありません。
新的学期,新的希望,随着开学脚步声的临近,相信每个中小学同学都有自己的憧憬和目标。
人生最美好的回忆就是校园生活。相信你现在觉得习以为常甚至厌倦的校园生活,在不久的将来就会成为你最美好的回忆,而现在你觉得压力山大的学习和苦恼,也会成为你日后最美好的回忆之一。
中国でのバレンタインデーは
2023/02/14中国のバレンタインデーの風習について
今日はバレンタインデーですね。
日本では1970年代から、チョコレートを贈る文化が根付いていきました。
高度成長経済の時期!
それより少し前、テレビのCMで「大きいことはいいことだ」とチョコレートの宣伝をしていました(知る人ぞ知る)
バレンタインデーといえば、女性から男性へチョコレートを贈り、愛を告白する日として親しまれているイベント。
毎年バレンタイン・シーズンになると、街のいたるところで、たくさんの種類のチョコレートが販売されています。
この「女性から男性へチョコレートを贈る」のは、日本独自だそうで、
女性が男性へ愛の告白の意味で贈るという習慣も日本だけだそうです。
バレンタインデーの習慣
1.新暦の毎年2月14日のバレンタインデーは欧米の伝統的な祭日で、この日にカードやバラを贈ったり、チョコレートを食べたりする習慣があります。
2.一般的に、男性が女性にこれらのプレゼントを贈り、あなただけだと熱い思いを伝えます。
中国語意訳:
1、每年的公历2月14日情人节是西方的传统节日,在这天人们有赠送贺卡和玫瑰花,吃巧克力的习俗。
2、一般情况下,男性送给女性这些礼物,用来表达对爱人用情专一、情感炙热。
中国での2月14日バレンタインデーのギフトランキングは?
2月14日バレンタインデーのギフトランキングは?
2月14日のバレンタインデーの贈り物といえば、1番目は間違いなくバラ、2番目はチョコレート、その他は女性が好むバッグや化粧品、香水などではないでしょうか。
ですから、男性が女性にバレンタインデーのプレゼントを送る場合、やはり相手の好むところに合わせ、ロマンティックなものを選んだり、実用的なものを選んだりします。
中国語意訳:
2月14日情人节礼物排行榜?
2月14日情人节礼物排行榜第一肯定是玫瑰花,第二那就是巧克力,其他的可能就是女生比较喜欢的包包,化妆品,香水之类的。
所以男生要送女生情人节礼物的话,还是要投其所好,有的是选浪漫的,有的是选实用的。
解説:排行榜 páihángbǎng ランキング、番付
投其所好 tóu qí suǒhào [成語]相手の好むところに合わせる。
有的~yǒude ある(人).ある(もの).【補足】繰り返しの形で用いることが多い。
一位はバラ!

中国でバレンタインデーのバラの値段はいくら?
普段は1本が3〜5元(約60~100円)のバラが、バレンタインデーには倍の10元(約200円)になることもあるそうです。
価格は少し高めですが、一年にロマンチックにバラを贈るのは何度もないので、大切な人のためにバレンタインデーは贅沢をする人が多いようです。
何本送る?
バレンタインデーには1、9、11、52、99本のバラを贈るのが一般的ですが、響きの良い数字や特別な意味を持つ数字で贈ったりします。
例えば、11本のバラは「一心一意」、99本のバラは「(九と久が同じ音なので)久しく末永く一緒にいたい」という意味が込められているそうです。
99本も買うと約2万円!すご~~い!
誰ですか?その分、現金で欲しいと言っているのは!(私か!)
-
 中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!
中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を学
中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!
中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を学
-
 中国語の文法地獄を抜け出す方法
中国語の文法地獄を抜け出す方法みなさん、こんにちは。 大家好! 文法が壁になる理由中国語学習において、多くの方
中国語の文法地獄を抜け出す方法
中国語の文法地獄を抜け出す方法みなさん、こんにちは。 大家好! 文法が壁になる理由中国語学習において、多くの方
-
 中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統
中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統みなさん、こんにちは。 大家好!中秋节快乐!今日10月6日は十五
中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統
中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統みなさん、こんにちは。 大家好!中秋节快乐!今日10月6日は十五
-
 速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法
速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法みなさん、こんにちは。 大家好!先日、中秋節に関する中国語の音声を用意
速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法
速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法みなさん、こんにちは。 大家好!先日、中秋節に関する中国語の音声を用意
-
 中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現
中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を勉強していて
中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現
中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を勉強していて