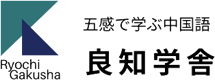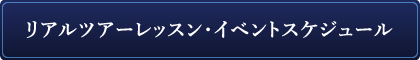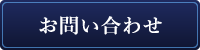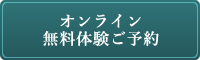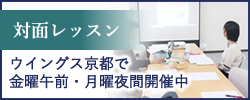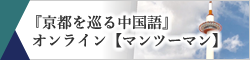- ホーム
- ブログ
ブログ
車いすラグビー、凄すぎる
2021/08/27【車いすラグビー】「凄すぎる」
パラリンピックの車いすラグビーは25日、日本が初戦でフランスを53-51で破りました。
車いすが音を立ててぶつかり合うプレーはすごい迫力!
男女混合の競技で、猛者のキン肉マン男子に混じって女子選手がいるのもすごい!

「車いすラグビー」どんな特徴があるのでしょうか?
轮椅橄榄球的项目特征 Lúnyǐ gǎnlǎnqiú de xiàngmù tèzhēng
轮椅橄榄球运动是专门为残疾程度较重的肢体残疾者而设计的一个集体球类项目。
参加比赛的运动员主要是颈椎损伤的运动员,除下肢必须依靠轮椅外,上肢还有不同程度的障碍。
它集安全性、竞技性和观赏性于一体,既突出运动员的个人技术,又强调团队配合。
比赛由男、女队员混合组队参加,轮椅橄榄球的正式比赛是在室内进行,攻防双方各上场4名运动员。
所有的运动员必须坐在手控轮椅上参加比赛,并符合国际轮椅橄榄球联盟的分级限定标准。
比赛过程中,允许轮椅之间进行接触。如当运动员持球或者企图阻断对方时,和对手发生激烈的碰撞。
但是一些危险的接触形式,如在对方轮椅后部攻击对方是不允许的,会造成犯规。
另外运动员之间也不能进行身体接触。
訳文:
車いすラグビーの特徴
車いすラグビーは、重度の身体障害を持つ人のために作られたチームスポーツです。
主に頸椎を損傷し、下肢は車いすに頼らざるを得ない選手や、上肢にも様々な障害がある選手がプレーしています。
安全性、競技性、観戦性が一体化し、選手の個人技が際立ち、チームワークが強調されます。
ゲームは男女混合で、車いすラグビーの公式試合は室内で行われ、攻撃と守備双方の4人の選手がプレーします。
すべてのプレーヤーは、手動の車いすで競技に参加し、国際車いすラグビー連盟によるクラス分けの限定基準を満たす必要があります。
試合中、車いす同士の接触は認められています。 例えば、プレーヤーがボールを保持したり、相手をブロックしようとすると、相手との激しい衝突が起こります。
しかし、相手の車いすの後部を攻撃するような危険な接触は許されず、ファウルになることもあります。
また、プレーヤー同士の身体的接触も禁止されています。
観戦しながら、「うわ〜うわ!大丈夫?」と声が出てしまいます。
轮椅橄榄球运动员们、加油!
車いすラグビーの選手のみなさん、がんばれ!
不要受伤 ! ケガしないでね。
パラリンピック特有の競技とは?
2021/08/26残奥会有哪些特有的运动项目?
Cán'àohuì yǒu nǎxiē tèyǒu de yùndòng xiàngmù?
パラリンピック特有の競技とは?
残奥会的运动项目大部分与奥运会一致,
Cán'àohuì de yùndòng xiàngmù dàbùfen yǔ Àoyùnhuì yízhì,
パラリンピックでは、オリンピックとほとんど同じ競技が行われます。
共设有22个大项539个小项。
gòng shèyǒu 22 gè dà xiàng 539 gè xiǎo xiàng
合わせて22競技、539種目が実施されます。
其中,羽毛球和跆拳道将首次作为残奥项目出现在东京赛场。
Qízhōng,yǔmáoqiú hé táiquándào jiāng shǒucì zuòwéi cán ào xiàngmù chūxiàn zài Dōngjīng sàichǎng
そのうちバドミントンとテコンドーは、東京大会で初めてパラリンピック競技として採用されます。
此外,残奥会还有两个特有的项目,硬地滚球和盲人门球。
Cǐwài,cán'àohuì háiyǒu liǎng ge tèyǒu de xiàngmù,yìng dìgǔnqiú hé mángrén ménqiú。
また、パラリンピック特有の2つの競技が行われます。それはボッチャとゴールボールです。

パラリンピック開会式開催
2021/08/25東京パラリンピック開会式開催
东京残奥会开幕式举行。Dōngjīng cán'àohuì kāimùshì jǔxíng
昨夜の開幕式をテレビで見ました。
入場行進での紹介で、病気や戦争で身体が不自由になった選手、それを乗り越えてこの大舞台に立っていると聞いて、
パラリンピックの選手たちはみな、たくさんの困難や挫折を味わって来ていること、その選手のひたむきな姿に学ぶべきところが多いと改めて思いました。
选手们身残却撒汗到竞技场上去拼搏这种精神本身都很值得我们去关注去学习。
Xuǎnshǒu mén shēncán què sā hàn dào jìngjìchǎng shàngqù pīnbó zhè zhǒng jīngshén běnshēn dōu hěn zhíděi wǒmen qù guānzhù qù xuéxí
選手たちは身体は不自由でも競技場で、汗を流し力いっぱい頑張るその精神自体に、私たちは注目し、学ぶ価値があります。
まさしく、
‟功夫不负苦心人”,肯下苦功,一定有成果。
‟gōngfu bú fù kǔxīn rén”, kěn xià kǔgōng,yídìng yǒu chéngguǒ
テレビで、競技を観戦し、パラアスリートたちに大きな声援を送りたいと思います。

パラリンピック開幕
2021/08/24
东京残奥会今天开幕 Dōngjīng cán'àohuì jīntiān kāimù.
東京パラリンピック今日開幕
第16届残奥会于8月24日至9月5日在东京举行,共设22个大项、539个小项,将有来自约160个国家和地区的4400名运动员参赛。
Dì 16 jiè cán'àohuì yú 8 yuè 24 rì zhì 9 yuè 5 rì zài Dōngjīng jǔxíng,gòng shè 22 gè dà xiàng、539 gè xiǎo xiàng,jiāng yǒu láizì yuē 160 gè guójiā hé dìqū de 4400 míng yùndòngyuán cānsài.
第16回パラリンピックは、8月24日から9月5日まで東京で開催され、22競技と539種目が行われ、約160の国と地域からの4,400名の選手が競い合います。
日本的第五波感染是由具有高度传染性的德尔塔变种引起的,这促使政府将东京和其他地区的疫情紧急措施延长至9月12日。
Rìběn de dì-wǔ bō gǎnrǎn shì yóu jùyǒu gāodù chuánrǎnxìng de Dé'ěrtǎ biànzhǒng yǐnqǐ de,zhè cùshǐ zhèngfǔ jiāng Dōngjīng hé qítā dìqū de yìqíng jǐnjí cuòshī yáncháng zhì 9 yuè 12 rì.
日本では、感染力の強いデルタ株による第5波の感染が発生しており、政府は東京などで発生している感染症の緊急措置を9月12日まで延長します。
上周五,残奥会主办方表示,残奥会将在“非常困难”的情况下举行,东京的医院已经在与疫情的战斗中人满为患。
Shàng zhōu-wǔ,cán'àohuì zhǔbàn fāng biǎoshì,cán'àohuì jiāng zài “fēicháng kùnnan” de qíngkuàng xià jǔxíng,Dōngjīng de yīyuàn yǐjīng zài yǔ yìqíng de zhàndòu zhōng rén mǎn wéi huàn.
パラリンピックの主催者は、金曜日、大会は「非常に困難な」状況下で開催され、東京の病院は疫病との戦いで、すでに過密状態にあると発表しました。
このようなコロナ禍ではありますが、国際大会の中止や練習場所の制限など様々な困難を乗り越えてきた選手たちの活躍を期待しています。
「チンジャオロース」の「ロース」とは
2021/08/23ピーマンは、中国語で‟青椒 qīngjiāo”

ピーマンを使った中華料理の代表格が「チンジャオロース」ですね。
授業で、「チンジャオロース」の「チンジャオ」は、青椒qīngjiāoピーマンのことですよ、というと
ある生徒さんが「ロース」は、「豚肉のヒレ、とかバラとかモモとかの部位のことですよね」と言うのを聞いて、
思わず大笑い。
私: いえいえ、「ロース」は‟肉丝 ròusī”、肉の細切りのことです。
生徒さん: 「ず〜と、「ロース」肉を使うから「チンジャオロース」だと思っていました。」
‟丝 sī” は、糸状の細いものを指し、料理では千切りや糸切り、細切りのことです。
「チンジャオロース」を作りましょう。

‟青椒肉丝”,食材来源广泛,炒制过程简单。成菜后,色泽美观,质嫩味美。
「チンジャオロース」(豚肉の細切りとピーマンの炒め物)は、材料が豊富で、簡単に作ることができます。 彩りも美しく、柔らかくて美味しいですよ。
材料:
猪肉瘦肉: 豚肉の赤身
青椒: ピーマン
淀粉: 片栗粉
蛋清: 卵白
鸡精: 鶏がらスープの素
葱姜:ネギとショウガ
青椒肉丝的做法步骤: チンジャオロースの作り方
1.青椒150g、洗净。
2.青椒去除尾部、从中间刨开去籽、去筋。
3.青椒切丝。
4.猪精瘦肉洗净切丝。
5.把切好的肉丝放入碗内加淀粉、蛋清、鸡精抓均上浆、腌制一会。
6.炒锅上火烧热、到油、至油温3-4成热时倒入肉丝翻炒。
7.待肉丝炒至发白断生时盛出装盘待用。
8.炒锅再次上火到底油爆香葱姜末、倒入青椒丝、肉丝调味、大火快炒。
9.最后用水淀粉勾薄芡、不可时间过长、否则肉丝变老、青椒丝变软、就不好吃了。
10.炒好的青椒肉丝、肉丝滑嫩、青椒丝脆爽。
訳文:
1.ピーマン150g を洗っておく。
2.ピーマンの先端を取り除き、真ん中からかき開き、種と筋を取り除く。
3.ピーマンを細切りにする。
4.豚の赤身を洗い、細切りにする。
5.細切れにした肉をボウルに入れ、片栗粉、卵白、鶏がらスープの素を加えてよく混ぜ合わせ」、しばらく置く。
6.フライパンを火にかけ、油を入れて、油が3〜4割の熱さになったら細切れ肉を入れて炒める。
7.細切れにした肉の色が変わったら、お皿に取り出す。
8.フライパンに再び油をひいて熱し、細切りのネギとショウガを炒め、細切りのピーマンを加えて、肉を戻し、味を整え、強火で手早く炒める。
9.最後に水溶き片栗粉でとろみをつける。時間をおくと肉が硬くなったり、ピーマンの細切りが柔らかくなったりしておいしくない。
10.出来上がったチンジャオロース、肉は滑らかで柔らかく、ピーマンの細切りはシャキッとしていますよ。
お肉を「ロース」切りにして、作ってみてくださいね。
-
 中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?
中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?みなさん、こんにちは。 大家好!先日、テキストに「风
中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?
中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?みなさん、こんにちは。 大家好!先日、テキストに「风
-
 中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社
中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社みなさん、こんにちは。 大家好!先日、金曜クラスの受講者のみなさんと一緒に、
中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社
中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社みなさん、こんにちは。 大家好!先日、金曜クラスの受講者のみなさんと一緒に、
-
 中国語初心者が最初の3ヶ月で押さえるべき学習ロードマップ
中国語初心者が最初の3ヶ月で押さえるべき学習ロードマップみなさん、こんにちは。 大家好!「中国語を勉強したいけ
中国語初心者が最初の3ヶ月で押さえるべき学習ロードマップ
中国語初心者が最初の3ヶ月で押さえるべき学習ロードマップみなさん、こんにちは。 大家好!「中国語を勉強したいけ
-
 オンライン中国語中級クラス終了と「子ども食堂」への寄付
オンライン中国語中級クラス終了と「子ども食堂」への寄付みなさん、こんにちは。 大家好!今年5月からスタートした
オンライン中国語中級クラス終了と「子ども食堂」への寄付
オンライン中国語中級クラス終了と「子ども食堂」への寄付みなさん、こんにちは。 大家好!今年5月からスタートした
-
 四声マスターへの近道!中国語の発音を劇的に改善する7つのコツ
四声マスターへの近道!中国語の発音を劇的に改善する7つのコツみなさん、こんにちは。 大家好!「中国語の発音が難
四声マスターへの近道!中国語の発音を劇的に改善する7つのコツ
四声マスターへの近道!中国語の発音を劇的に改善する7つのコツみなさん、こんにちは。 大家好!「中国語の発音が難