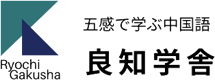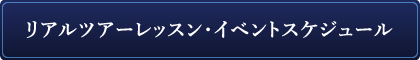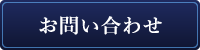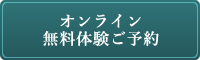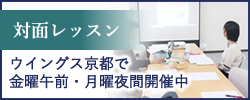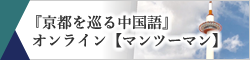- ホーム
- ブログ
ブログ
発表:中国初のコロナワクチン全国民に無料で提供
2021/01/05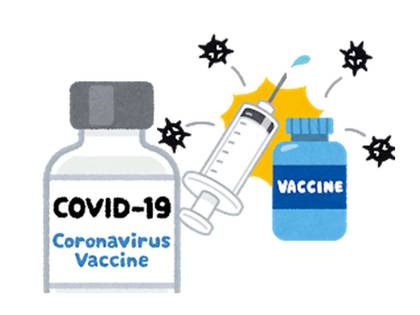
中国cctv.com 2020年12月31日のニュースから
中国政府筋は、
中国で初めての新型コロナウィルスワクチンの
条件付き発売を承認し、
全国民に無料で提供していくと発表しました。
国薬集団(シノファーム)中国生物北京公司の
新型コロナウィルスワクチンⅢ期臨床試験の分析結果によると、
このワクチンは
WHOと中国国家薬監局の関連基準と条件付き販売基準を満たすものだとしています。
そこで、国家薬監局は、企業が引き続きⅢ期臨床試験を展開し、
予防接種後の異常反応などの各情況をまとめ上げ、
直ちにワクチンの説明書やラベルなどの更新を急がせることにしています。
新型コロナウィルスワクチンの緊急接種が今年6月から始まってから、
接種は累計450万回以上に及びますが、
軽度発熱の割合は0.1%に満たず、
アレルギーなど比較的悪い反応の発生率はおよそ100万分の2で、
これは中国のコロナウィルスワクチンが安全であることを証明しており、
今後は高齢者や基礎疾患のある人など重症化リスクグループと
普通な人に対し、このワクチンを順に接種していくとしています。
田中くん、きっと間違ってる?
2021/01/05
今年の元日から中国語の表現でまちがいやすいところの解説を始めました。
今日は第5回です。
文中どこがおかしいのか、先ず考えてみてください。
分かった方・・・さすが!
分からなかったあなた・・・・・・・これをきっかけに覚えて下さいね。
今日の文章
我估计田中同学这道题一定做错了。
どこが間違っているでしょう?
========================
この文章では、“估计”は推測したり,見積もること
そして“一定”は、必ず、きっとの意味なので、
“估计”と“一定”をいっしょに使うのは矛盾しています。
正しくは“一定”を取って、
“我估计田中同学这道题做错了。
Wǒ gū jì Tián zhōng tóng xué zhè dào tí zuò cuò le.”
というふうにします。
小さな間違いを修正して、大きな成果に結び付けましょう。
イラストでは、鉛筆を転がして解答していますが、
それが案外当たっているかも!?
もう、まちがえない!実践チュウゴクゴ(4)
2021/01/04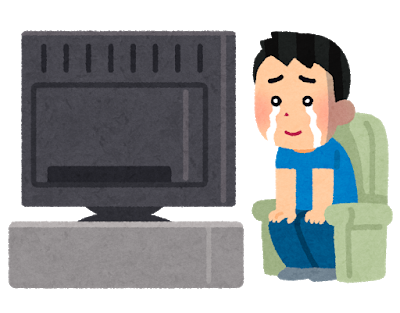
もう今日から仕事始めです。
1月1日から中国語の表現でまちがいやすいところの解説を始めました。
文中どこがおかしいのか、先ず考えてみてください。
正解したあなた・・・・・・・すご〜い!
分からなかったあなた・・・・・・・これをきっかけに覚えて下さいね。
今日の文章
看了元旦播出的那部电视剧,都留下了深刻的印象。
どこが間違っているでしょう?
========================
この文章では、「だれ」に、深刻的印象を留下したのかが欠けています。
正しくは
“看了元旦播出的那部电视剧,给我留下了深刻的印象。
Kàn le Yuán dàn bō chū de nà bù diàn shì jù ,gěi wǒ liú xià le shēn kè de yìn xiàng .”
あるいは
“看了元旦播出的那部电视剧,使我留下了深刻的印象。
Kàn le Yuán dàn bō chū de nà bù diàn shì jù ,shǐ wǒ liú xià le shēn kè de yìn xiàng .”
もしくは
“我看了元旦播出的那部电视剧,都留下了深刻的印象。
Wǒ kàn le Yuán dàn bō chū de nà bù diàn shì jù ,dōu liú xià le shēn kè de yìn xiàng .”
というふうにします。
小さな間違いを修正して、大きな成果に結び付けましょう。
あなたはどの番組が印象深かったですか??
やはり、アレですね!
もう、まちがえない!実践チュウゴクゴ(3)
2021/01/03
元日から中国語の表現でまちがいやすいところの解説を始めました。
文中どこがおかしいのか、先ず考えてみてください。
正解したあなた・・・・・・・すご〜い!
分からなかったあなた・・・・・・・これをきっかけに覚えて下さいね。
今日の文章
最后她终于考上了京都大学。
どこが間違っているでしょう?
========================
この文章では、“最后”と“终于”が重複していますね。
どちらかひとつにしましょう。
正しくは
“最后她考上了京都大学。
Zuì hòu tā kǎo shàng le Jīng dū dà xué .”
あるいは
“她终于考上了京都大学。
Tā zhōng yú kǎo shàng le Jīng dū dà xué ”
というふうにします。
小さな間違いを修正して、大きな成果に結び付けましょう。
受験の季節、
受験生の方、ラストスパート 最后冲刺zuì hòu chōng cì
身体に気を付けて頑張ってください。
もう、まちがえない!実践チュウゴクゴ(2)
2021/01/02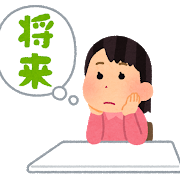
昨日から中国語の表現でまちがいやすいところの解説を始めました。
文中どこがおかしいのか、先ず考えてみてください。
正解したあなた・・・・・・・すご〜い!
分からなかったあなた・・・・・・・これをきっかけに覚えてね。
今日の文章
对于调动工作这个问题上,我曾周密地考虑过。
どこが間違っているでしょう?
========================
この文章では、“对于……上 ”の部分がおかしいですね。
“对于”と“上”はこの場合いっしょに使いません。
正しくは
“对于调动工作这个问题”Duì yú diào dòng gōng zuò zhè ge wèn tí
あるいは
“在调动工作这个问题上zài diào dòng gōng zuò zhè ge wèn tí shàng”というふうに、
在……上にします。
小さな間違いを修正して、大きな成果に結び付けましょう。
-
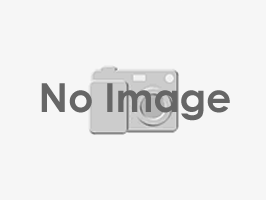 中国語初心者のための学習モチベーション維持術
中国語初心者のための学習モチベーション維持術皆さん、こんにちは!大家好!中国語の学習を始めたばかりの方にとって
中国語初心者のための学習モチベーション維持術
中国語初心者のための学習モチベーション維持術皆さん、こんにちは!大家好!中国語の学習を始めたばかりの方にとって
-
 中国語で知る秋の養生法!「食欲の秋」は健康的に!
中国語で知る秋の養生法!「食欲の秋」は健康的に!みなさん、こんにちは!大家好!まだ日中は暑いですが、朝晩はずい
中国語で知る秋の養生法!「食欲の秋」は健康的に!
中国語で知る秋の養生法!「食欲の秋」は健康的に!みなさん、こんにちは!大家好!まだ日中は暑いですが、朝晩はずい
-
 中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!
中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を学
中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!
中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を学
-
 中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!
中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を学
中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!
中国語のリスニングを上達させる3つのコツ:試験も会話も自信を持って!みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を学
-
 中国語の文法地獄を抜け出す方法
中国語の文法地獄を抜け出す方法みなさん、こんにちは。 大家好! 文法が壁になる理由中国語学習において、多くの方
中国語の文法地獄を抜け出す方法
中国語の文法地獄を抜け出す方法みなさん、こんにちは。 大家好! 文法が壁になる理由中国語学習において、多くの方