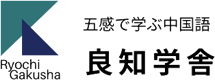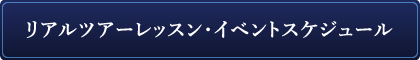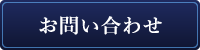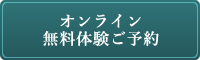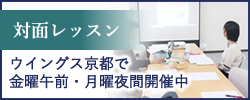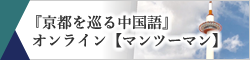- ホーム
- ブログ
ブログ
気になる二の腕の「振袖」、中国語では「蝶々腕」
2021/04/09どこからどこまでが、‟手shǒu”??
「腕」って???
前に「足編」で、‟脚、腿”はどこからどこまでかを紹介しました。
今回は「手編」です。

手首から先の部分は、‟手shǒu”。
手首から肩まで、いわゆる日本語で「腕、うで」は‟胳膊gēbo、臂bì”
これを更に細かく分けると、
ひじから手首までを、‟前臂qiánbì”
肩からひじまでを‟上臂shàngbì”
日本語の「腕」という漢字は、中国語では「手首、足首」を指すので、注意しましょう。
手の関連単語を紹介します。
手背 shǒu bèi→手の甲
指甲 zhǐjia→爪
拇指 mǔzhǐ→親指
食指 shí zhǐ→人差し指
中指zhōng zhǐ→中指
无名指 wú míng zhǐ→薬指
小指 xiǎo zhǐ→小指
手掌 shǒu zhǎng→手のひら
手心 shǒu xīn→手の平の中央
‟手心”は「手の中心」の意味で、日本語で言う「手ごごろを加える、手加減する」の「手心」ではないので、注意しましょう。
二の腕のたるみ
これから気温が上がってくると、半袖を着る機会が増えてきますが、そんな時に気になるのが「ニノウデ」すなわち「振袖」と呼ばれる贅肉のたるみ。
がんばって鍛えても、なかなか二の腕のたるみは取れませんよね。
この「二の腕のぜい肉」を中国語で「蝶々腕」というのは、おもしろいです。
蝴蝶臂
蝴蝶臂就是对一种手臂比较肥的形象的叫法。因为当手臂足够肥的时候,特别是你的上手臂比较肥,当你手臂平举的时候会有从腋下到手肘之间的肥肉下垂,看上去是一个小扇形的。有人就形象的称之为蝴蝶臂。
蝶々腕
蝶々腕は、すなわち太った腕に対しての言い方です。腕が太っていると、特に上腕はとっても太っています。腕を広げて上げた時、脇から肘にかけての肥えた肉が垂れ下がって、小さな扇形のように見えるので、ある人はこれからイメージして蝶々腕と呼びます。
「振袖」にせよ、「蝶々腕」にせよ、なんかキレイでいいですね。
聞こえはいいのですが、やっぱり無くしたい!
京都は名勝旧跡がたくさんあります。
今回は徳川将軍ゆかりの地、二条城で歴史の解説と中国語のレッスンを行います。
日時:4月17日(土) 10:00〜12:00
場所:二条城
是非ご参加ください。
詳細とお申込みはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
https://ryochigakusha.pw/webform_15.html?rspdt=2021-04-17&rsptm=10-00&rspdt2=2021-04-17&rsptm2=12-00&rscdid=356&code_val_6=gpvoqrtu5gmemsdpotk6ydczca
【オンラインレッスン 無料体験会開催】
日時:4月29日(木) 11:00〜11:30
中国語でも「漢字」を使いますが、発音は全く違います。
自分の名前を中国語でどういうふうに言うの?
中国語に興味のある方、まずはここから始めましょう。
詳細とお申込みはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
中国語「的」の使い方、まちがいさがし
2021/04/08コロナ禍で会社の仕事の仕方も様変わりし、当初は戸惑うことばかりだったのに、次第に慣れてきたという方も多いのではないでしょうか。
ちなみに、「私の会社」と中国語で言うときは、‟我们公司wǒmen gōngsī”と、私のにあたる「的」は普通付けず省略します。
人称代名詞(話し手、受け手、および談話の中で指定された人や物を指す代名詞)が、連帯修飾語(名詞を詳しく説明して飾ることば)として、
親族名称や所属機関等を表す中心語(主になることば)にかかる時は、
「的」を省略できます。
例えば、
親族関係→‟我爸爸”、‟你妈妈”、‟她姐姐”
所属機関→‟我们学校”、‟他们单位”(单位は、日本語で勤め先、勤務先、所属先のこと、学校で必要な単位や、重さや長さの単位ではありませんので注意してくださいね)
など「「的」は省略します。
ここで、
もう、まちがえない!実践チュウゴクゴ(24)
中国語の表現でまちがいやすいところの解説をします。
文中どこがおかしいのか、先ず考えてみてください。
正解したあなた・・・・・・・なかなかのレベルですね〜〜〜!
分からなかったあなた・・・・・・・これをきっかけに覚えて下さいね。
今日の文章
我还没看完你给我介绍那本小说呢!
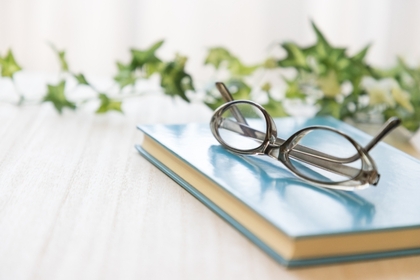
どこが間違っているでしょう?
========================
文中の‟你给我介绍那本小说”の部分で、,構造助詞「の」が欠けていて、文の構造がはっきりせず、意味がわかりません。
この文章の主幹は「私は小説を読む」です。
どんな小説かというと、「あなたが私に紹介してくれた」、「その」、小説です。
「あなたが私に紹介してくれた」、「その」、どちらも目的語「小説」の修飾語なので
主述語群「あなたが私に紹介してくれた」の後に、修飾語のしるしとなる「的」を付けましょう。
正しくは
我还没看完你给我介绍的那本小说呢!
Wǒ hái méi kàn wán nǐ gěi wǒ jièshào de nà běn xiǎoshuō ne.
となります。
文頭で、「的」を省略できる例を挙げました。
まちがいさがしでは「的」を必ずつける例を紹介しました。
もう〜〜、いつ省略?いつ付ける?わからない!という気持ちになりますね。
ことばは、算数ではないので「AイコールB」とはいきません。
外国語をそのまま日本語に当てはめてるのは、無理があるときもあります。
やはり、例文を多く見て、『体得』するのがおすすめです。
【京都の二条城で中国語を学びませんか?】4月17日(土) 10:00〜12:00
京都は名勝旧跡の宝庫。
今回は見どころいっぱいの、二条城で中国語のレッスンを行います。
日時:4月17日(土) 10:00〜12:00
場所:二条城
是非ご参加ください。
詳細とお申込みはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
https://ryochigakusha.pw/webform_15.html?rspdt=2021-04-17&rsptm=10-00&rspdt2=2021-04-17&rsptm2=12-00&rscdid=356&code_val_6=gpvoqrtu5gmemsdpotk6ydczca
自分の名前を中国語でどういうふうに言うの?
中国語に興味のある方、まずはここから始めましょう。
中国語の特徴や基本をお話しした後、
京都の名所旧跡のビデオを使って、小旅行気分でフレーズを練習します。
以前、中国語を学んだことがあるけど、また再開してみようという方も是非ご参加ください。
詳細とお申込みはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
https://ryochigakusha.pw/webform_17.html清明節、中国では国内旅行が大盛況
2021/04/07今日のニュースによりますと、大阪府で新型コロナウイルスへの新たな感染者が、過去最多の800人台後半になる見通しだそうで、引き続き注意しなければなりませんね。
一方、中国では国内旅行がすごい盛況です。
4月4日は清明節で、4月3日(土)〜5日(月)の3連休でした。
清明節の風習としては、祖先の墓を参り、草むしりをして墓を掃除する日で、‟扫墓节sǎo mù jié”「掃墓節」とも呼ばれます。
春を迎えて郊外を散策する日でもあり、‟踏青节tà qīng jié”「踏青節」とも呼ばれます。「青」を「踏む」とは、何とも詩的ですね。
中国のニュースtraveldaily.cnによりますと、
清明假期:国内旅游出游1.02亿人次,实现旅游收入271.68亿元。
综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据,经文化和旅游部数据中心测算,2021年清明节假期,全国国内旅游出游1.02亿人次,按可比口径同比增长144.6%,恢复至疫前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元,同比增长228.9%,恢复至疫前同期的56.7%。国内旅游市场正在有序复苏,由于近程旅游占比高、旅游产品价格低、景区减(免)票等原因,旅游消费完全恢复尚需时日。清明节假期,全国文化和旅游系统未发生重特大安全生产事故,未发生疫情通过文化和旅游系统传播事件。
訳してみました。
清明の休暇: 国内旅行者のべ1億200万人、観光旅行収入は271.68億元(4,560億1800万円)に達しました。
各地の文化観光部門、通信事業者、オンライン旅行サービス事業者のデータをまとめた、文化観光部データセンターの推計によりますと、
2021年の清明節休暇に、中国で国内旅行に行った人はのべ1億200万人で、前年同月比144.6%増え、コロナ前の94.5%に回復しました。
国内旅行収入は271億6800万元(4,560億1800万円)、前年比228.9%増加し、コロナ前の56.7%まで回復しました。
国内の旅行市場は段階的に回復していますが、近距離旅行の割合が高い、旅行商品の価格が安い、観光地のチケットが割引や無料になるなどのため、旅行消費が完全に回復するにはまだ時間がかかりそうです。
清明節の連休期間中、全国の文化観光旅行システムでは重大な安全生産事故は発生せず、文化観光旅行による感染はありませんでした。
日本でもそんな日が早く来てほしいものです。

京都は名勝旧跡がたくさんあります。
今回は徳川将軍ゆかりの地、二条城で歴史の解説と中国語のレッスンを行います。
日時:4月17日(土) 10:00〜12:00
場所:二条城
是非ご参加ください。
詳細とお申込みはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
https://ryochigakusha.pw/webform_15.html?rspdt=2021-04-17&rsptm=10-00&rspdt2=2021-04-17&rsptm2=12-00&rscdid=356&code_val_6=gpvoqrtu5gmemsdpotk6ydczca
日時:4月29日(木) 11:00〜11:30
中国語でも「漢字」を使いますが、発音は全く違います。
自分の名前を中国語でどういうふうに言うの?
中国語に興味のある方、まずはここから始めましょう。
詳細とお申込みはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
https://ryochigakusha.pw/webform_17.htmlきれいになった清水の舞台から、もしも・・・なら
2021/04/07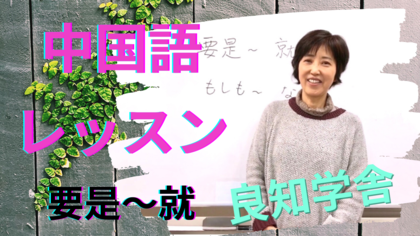
「もしも〜なら・・・」は中国語で、‟要是〜 就・・・”で表せます。
‟要是yàoshi,”以外にも‟如果rúguǒ”や‟假如jiǎrú”もありますが、今日は‟要是〜 就・・・”を使った文章を解説します。
動画を作りましたので、ご覧ください
例えば、
京都の古い寺院、「清水寺」に、行ったことがある方も多いと思います。
「清水の舞台からとびおりる」のことわざでも有名な舞台は最近修理が終わり、生まれ変わったようにピカピカ。
きれいになった舞台、高さは変わらず約12m、ビル4階分の高さに相当するそうですから、もしもここから落ちたら、どうなる???
要是从这儿掉下去就活不了了。
Yào shì cóng zhè r diào xià qù jiù huó bù liǎo le
もしも、ここから落ちたらお陀仏だ。
要是〜就・・・で、「もしも〜なら・・・」
从は、起点を表す「…から.…より」
掉は、「落ちる、落とす」
下去は、複合方向補語で、動詞の後に用いて、人や事物が話し手から離れて下方に向かって移動していくことを表します。
活は、「生きる、生存する、生命を保つ」
〜不了は、〜にはなり得ない、…しっこない、…するようなことはないという意味で、好ましくない結果を招く動詞や形容詞の後に用いますね。
そして、これらが表す動作や状態が起こり得ないことを表します。
発音に注意してください。bù liǎo というふうに、了はliǎo と読みます。
例文をもう二つ
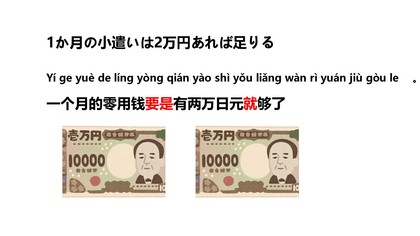
2万円で足りますか???
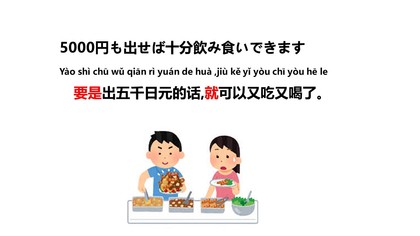
バイキングで5000円だと、結構いいのが食べられますね。
「もしも〜なら・・・」、‟要是〜 就・・・”使う場面がたくさんありますので、ぜひ作文してみてください。
【世界遺産の二条城で中国語を学びませんか?】
今回は徳川将軍ゆかりの地、二条城で歴史の解説と中国語のレッスンを行います。
日時:4月17日(土) 10:00〜12:00
場所:二条城
是非ご参加ください。
詳細とお申込みはこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
https://ryochigakusha.pw/webform_15.html?rspdt=2021-04-17&rsptm=10-00&rspdt2=2021-04-17&rsptm2=12-00&rscdid=356&code_val_6=gpvoqrtu5gmemsdpotk6ydczca
日時:4月29日(木) 11:00〜11:30
中国語でも「漢字」を使いますが、発音は全く違います。
自分の名前を中国語でどういうふうに言うの?
中国語に興味のある方、まずはここから始めましょう。
詳細とお申込みはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
https://ryochigakusha.pw/webform_17.html
サンガスタジアムで「フレー、フレー」
2021/04/05スタジアム 、中国語では‟球场qiúchǎng”
先日、京都亀岡のサンガスタジアムのそばを通りました。
環境問題や資金問題、いろいろあったそうですが、2018年1月20日に起工し、二年後の2020年1月11日に竣工。

ここは、サッカー‟足球zúqiú”、
ラグビー‟橄榄球gǎnlǎnqiú”、
アメリカンフットボール‟美式足球měi shì zú qiú”
などの専用球技場です。
フィールドの広さは南北126m×東西84mで、亀岡駅下車後、徒歩3分で到着。
スタジアムで、〔運動場〕の意味としては、‟运动场yùndòngchǎng,”や‟体育场tǐyùchǎng”とも言い、
例えば
这个体育场可以容纳21600人。
Zhè ge tǐ yù chǎng kě yǐ róng nà 21600rén.
このスタジアムは21600人入ります。
2020年2月9日在这个体育场首次举行了足球赛。
2020nián 2yuè 9rì zài zhè ge tǐ yù chǎng shǒu cì jǔ xíng le zú qiú sài 。
2020年2月9日このスタジアムで初めてサッカーの試合が行われました。
関連の言葉を紹介すると、
サッカーファン ‟足球迷zú qiú mí”
「迷」わされるほど、好きになる!
応援する、声援する ‟助威 zhùwēi”
応援してチームの「威」力を助ける!
応援団 ‟拉拉队 lālāduì”
応援団は、19世紀にアメリカのプリンストン大学ではじまり、
「フレー、フレー」と言う発声が
中国語では「ラー、ラー」と聞こえたので、‟拉拉队 lālāduì”になったとのことです。(百度より)
「フレー」が「ラー」に変わったとは、オドロキですね。
今回は威風堂々、二条城で
中国語のレッスンを行います。
日時:4月17日(土) 10:00〜12:00
場所:二条城
是非ご参加ください。
詳細とお申込みはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
https://ryochigakusha.pw/webform_15.html?rspdt=2021-04-17&rsptm=10-00&rspdt2=2021-04-17&rsptm2=12-00&rscdid=356&code_val_6=gpvoqrtu5gmemsdpotk6ydczca-
 中国語初心者必見!1日10分で続けられる超簡単習慣3つ
中国語初心者必見!1日10分で続けられる超簡単習慣3つ大家好、みなさん、こんにちは。「中国語に興味はあるけど、
中国語初心者必見!1日10分で続けられる超簡単習慣3つ
中国語初心者必見!1日10分で続けられる超簡単習慣3つ大家好、みなさん、こんにちは。「中国語に興味はあるけど、
-
 【2026年お正月】中国語で新年挨拶!すぐ使える簡単フレーズ4選
【2026年お正月】中国語で新年挨拶!すぐ使える簡単フレーズ4選新年あけましておめでとうございます。 年が明
【2026年お正月】中国語で新年挨拶!すぐ使える簡単フレーズ4選
【2026年お正月】中国語で新年挨拶!すぐ使える簡単フレーズ4選新年あけましておめでとうございます。 年が明
-
 【中国語文法】初心者が最初につまずく「了」の使い方|コツを押さえて話せる中国語へ
【中国語文法】初心者が最初につまずく「了」の使い方|コツを押さえて話せる中国語へ大家好、みなさん、こんにちは。
【中国語文法】初心者が最初につまずく「了」の使い方|コツを押さえて話せる中国語へ
【中国語文法】初心者が最初につまずく「了」の使い方|コツを押さえて話せる中国語へ大家好、みなさん、こんにちは。
-
 中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その1
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その1大家好、みなさん、こんにちは。
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その1
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その1大家好、みなさん、こんにちは。
-
 中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その2
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その2大家好、みなさん、こんにちは。
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その2
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その2大家好、みなさん、こんにちは。